1. 相続とは?
相続とは、亡くなった人の財産や負債を家族や親族が引き継ぐことを指します。財産だけでなく、借金(負債)も相続対象になります。
2. 相続の開始時点
相続は、死亡した瞬間から自動的に発生します。その後、遺産分割や登記などの手続きが必要となります。
3. 相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人。子どもがいない場合、親(直系尊属)が相続。親がいない場合、兄弟姉妹が相続。
民法では相続順位は次のように定められています:
- 第1順位: 配偶者 & 子ども
- 第2順位: 配偶者 & 直系尊属(両親・祖父母)
- 第3順位: 配偶者 & 兄弟姉妹
4. 法定相続分
遺言がない場合、民法に基づいて相続分が決まります。 例:配偶者 & 子どもの場合、配偶者が1/2、子どもが1/2(子どもが複数の場合、均等に分けられます)。
5. 遺言の重要性
相続は、死亡した瞬間から自動的に発生します。その後、遺産分割や登記などの手続きが必要となります。
- ✅自筆証書遺言
- ✅公正証書遺言
- ✅秘密証書遺言 中でも公正証書遺言は最も信頼性が高いです。
6. 相続放棄と限定承認
相続放棄: すべての財産と負債を放棄(手続きは家庭裁判所で行う)。
限定承認: 財産の範囲内で負債を引き継ぐ。
7. 相続税の基礎控除
相続税は、遺産総額から基礎控除を引いた額に対して課税されます。計算式は以下の通りです:
- 基礎控除 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が3人(配偶者+子2人)の場合:
遺産総額が4,800万円以下なら、相続税はかかりません。
基礎控除 = 3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円
限定承認: 財産の範囲内で負債を引き継ぐ。
8. 遺産分割協議
相続人全員で遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」を行い、協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
もし協議がまとまらなければ、家庭裁判所で「遺産分割調停」が行われます。
9. 相続登記の義務化(2024年4月1日~)
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記が必要となり、未登記の場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
10. 相続税の申告期限
相続税の申告は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生します。納付が難しい場合は、延納や物納の制度を利用することができます。
まとめ
- 相続は死亡した瞬間から自動的に発生します。
- 相続人や相続分は民法で定められています。
- 遺言がある場合、法定相続分に関係なく遺産を分けられます。
- 相続放棄や限定承認を利用して借金を避けることができます。
- 相続税の基礎控除や相続税の申告は期限内に行う必要があります。
- 相続登記は2024年から義務化されました。




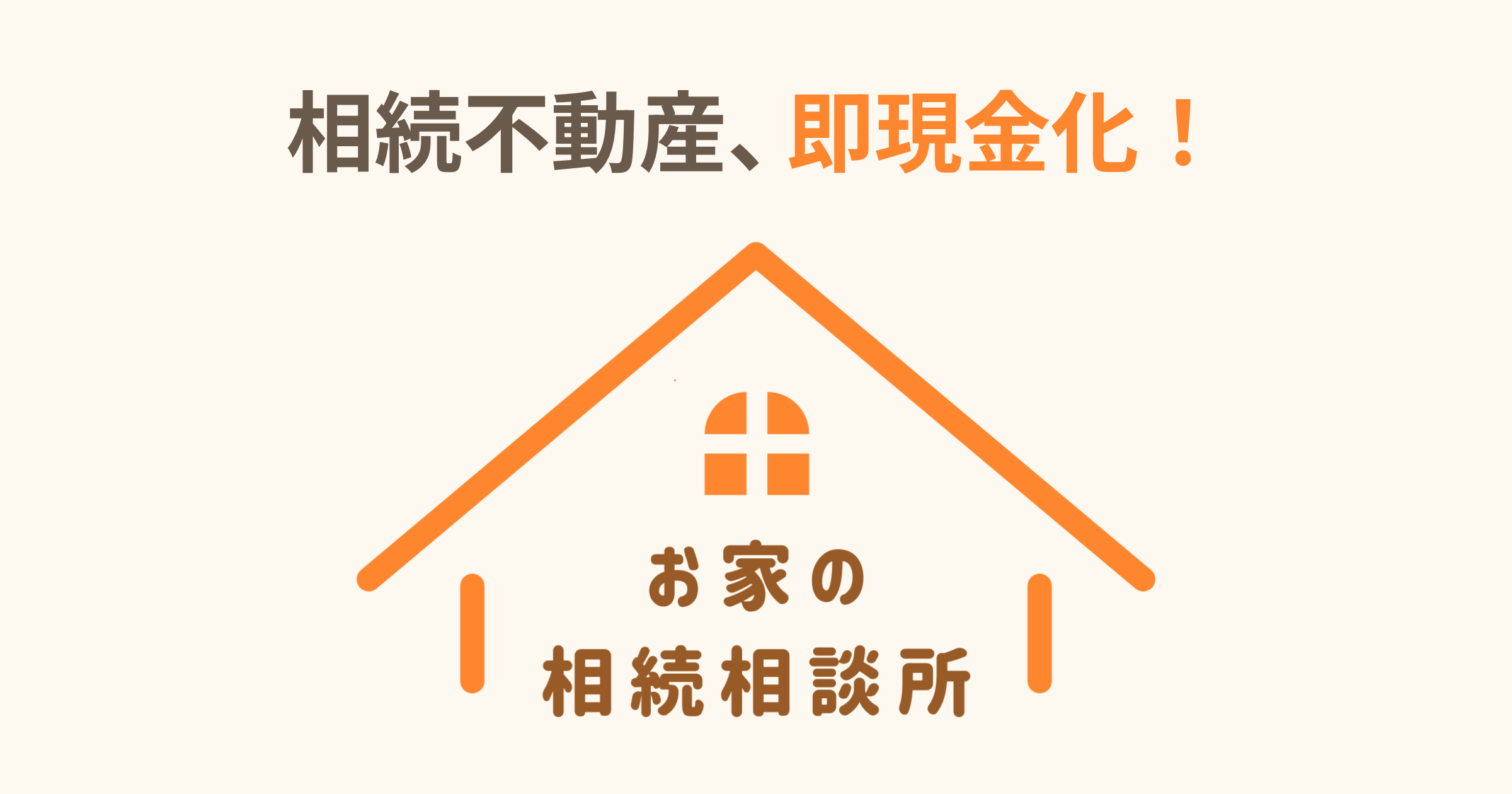
 前のページへ
前のページへ